粉飾決算は昔からありましたし企業規模は関係ありません。大企業でも不正な会計処理は行われてきましたし、非上場の中小企業においても、粉飾決算の発覚をきっかけとする倒産が多発しています。
そこで金融庁は、粉飾等の不適切な会計処理や不正行為による突発的な与信費用の発生を防ぐため、信用リスク管理体制を強化するよう金融機関に促してきましたし、令和7年6月に「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート(2025)」を公表しました。
主な粉飾方法
銀行は融資先から提出された決算書について、何らかの粉飾が行われていると考えたほうがいいです。そこで主な手口をいくつかご紹介します。
架空売上高の計上
代表的な粉飾方法です。売上高がそのまま利益になるため、大規模な粉飾したい企業が使う方法です。それに成長力のある企業に見せることもできます。
企業は黒字決算にしやすいメリットはありますが、輸出売上等を除いて消費税が増えるデメリットもあります。
在庫の水増し
在庫(棚卸資産のこと、商品、製品、原材料、仕掛品など)を増やすことで利益が増加します。期末在庫が増えれば原価が減少するためです。
在庫の水増しは利益が増えても法人税は増加しますが、売上高の架空計上とは異なり消費税に影響はありません。したがって、こちらもよく行われる粉飾方法です。
未払分の仕入高や外注費の未計上
支払済みの仕入高等を削除すれば現預金残に影響が出ますが、未払いであればその仕訳を削除しても影響はありません。仕入高や外注費は売上高ほどではないにしても、金額が大きいですから粉飾で使いやすい方法になります。
融資取引のない銀行口座に多額の預金計上
融資取引のない銀行に多額の預金があるようにする方法です。普通預金や当座預金を使う場合もありますが、架空の定期預金が存在するようにしている場合もあります。
減価償却費の未計上
固定資産を保有する企業では、販管費や製造原価報告書の中に減価償却費が計上されているはずです。
これまで減価償却費が発生していたにもかかわらず、大きく減少していたり、完全な未計上であれば、利益を出すために粉飾が行われています。
費用等を資産計上
本来は赤字決算だが、それを隠すため費用を資産計上します。あるいは架空または不良資産を消すために固定資産に振り替えることもあります。
主な粉飾決算の見抜き方
粉飾決算を行なえば、決算書には何らかの異常が表れます。
利益率の変化
粉飾決算は主に赤字を黒字に装うことが目的ですから、代表的な粉飾方法であり、売上高あるいは在庫の架空計上により利益が増加します。したがって、一番上にある売上総利益率(粗利益率)に異常が表れます。今まで以上に良くなるのです。
回転期間の異常
粉飾が行われた結果、異常が表れやすいのが売上債権(売掛金等)、棚卸資産(商品、製品等)、仕入債務(買掛金等)です。
粉飾の結果、売上債権や棚卸資産は増加しますし仕入債務は減少します。そこで月商等を用いて回転期間を計算すると、売上債権や棚卸資産は長期化し、仕入債務は短縮化します。
架空資産・不良資産の増加
費用を減らすために貸付金等資産への振り替えや、未計上にすることで存在しない現金が出てきます。また、回収不能債権や販売見込みのない商品等の不良資産も増加します。
同業他社との比較
利益率や回転期間等を同業他社との比較することはかなり参考になります。業種は一緒でも詳しい業務内容が異なれば、必ずしも一致するものではありませんが、その場合はなぜ差があるのかを確認すれば済むことです。
また、業界全体が横ばいで推移している時に、売上高が増加するようなら利益率に異常が出ないよう売上高と仕入高の両方を計上していることも考えられます。
統計以上に多い粉飾決算
銀行員のみなさんが考える以上に粉飾された決算書は多いです。当社へ相談に来られる企業の多くは程度の差はあれ粉飾をしています。
大企業と中小企業では異なる会計制度と実態
大企業でも粉飾決算が問題になることはあります。ただ、通常、非上場の中小企業は、財務諸表監査を受ける義務はありません。それに中小企業の決算書作成目的は、税務申告のために行われる性格が強いため、利益を少なくすれば問題になるが、多くする分には問題ないと考えます。
そのため、利益が多ければ税務調査で指摘されるリスクが減り、銀行との融資取引にもメリットがあると経営者は考えるのです。
決算処理の信頼性に関する調査
東京商工リサーチが今年8月に実施した調査「不適正会計に関するアンケート調査」によると、「自社の決算処理は信頼性が高いと言い切れるか」との問いに、「言い切れる」と答えた割合は87.9%でした。
ただし、これは信用調査会社のアンケートですから、ある程度割り引いて見る必要があるでしょう。つまり信頼性の低い決算書が調査結果以上に存在するかと思います。
決算書以外の注意すべき点
粉飾決算を見破る方法としては、これまで申し上げように決算書から異常を見つけることが中心になるように思われますが、それ以外にも注意すべき箇所はあります。
情報開示の姿勢
決算書が完成したら、ほとんどの経営者は取引銀行に提出するのを知っています。今まで依頼する前に提出されたものが、こちらからお願いしてから出るようでは、あまり積極的に提出したくない内容なのだろうと考えられます。
決算書だけを提出し勘定科目内訳明細書の開示を渋るのも要注意です。必要以上の情報開示は不要だと経営者にアドバイスするコンサルタントがいます。それは見せたくない相当な理由があるケースがほとんどです。
回収不能になった売掛債権がある、販売が困難な商品がある、経営者へ多額の貸付金などの存在です。
それは決算書に限らず試算表や資金繰り表等、他の書類でも一緒です。遅れるようになった、または提出されないようになってきたら、かなり業績が悪い、粉飾するのに時間がかかっていると考えられます。
外部環境
融資先の業種が業界全体では縮小傾向であるにもかかわらず、売上高が伸びているような場合、確かにそのようなことがないとはいえませんが、かなり他社よりも強みがあるからでしょう。それがないにもかかわらず好調なようであれば注意が必要です。
売上高だけでなく他の数字も同業他社比で確認しましょう。業界の平均値はあくまでも全体での平均値ですから、ずれがあったからといって直ちに異常だとは断言できませんが、どうしてその差が出ているのか、粉飾なのか、それとも技術力などで強みがあるのか調べるきっかけになります。
会計監査人等
会社法上の大企業ならば会計監査が義務付けられています。しかし、中小企業では必要ありません。税理士がその役割を担っている場合もありますが、多くは適正な税務申告をメインにしています。
また、税理士も顧問先獲得に苦労しています。顧問先から粉飾行為であっても求められると、断りにくい立場でもあります。
その税理士ですが、頻繁に変更されていないでしょうか。頻繁な変更があったとすれば、不正な作業の依頼が原因で断られているかもしれません。また、過去に他社で粉飾が明らかになった決算書を作成した税理士の署名がないかにも注意してください。複数社の粉飾に関与している可能性があります。
関係会社
1人の経営者が経営する企業が1社だけとは限りません。複数の企業のトップになっていることもあります。役員ではないが株主になっている場合もあります。
関係会社へ多額の商品を販売し赤字を回避していることがあります。
もちろん事業内容に関連性があれば、取引が発生することは問題ありません。しかし、関連性がまったくない、あるいは取引が発生する期とそうでない期があるなら注意したほうがいいでしょう。
融資先のビジネスをよく理解する
銀行員は融資先のビジネスをよく理解してください。運送業、印刷業など、業種は知っていても、具体的にどのようなものを製造しているのか、販売しているのか、もう少し踏み込んで理解したほうがいいです。
そして主な売上先、仕入先から何を仕入れているのか、外注先にどのような業務を依頼しているのか、入金や支払いの条件についても確認しておきます。そうすれば粉飾発見の手掛かりになります。
また分かったつもりになっていることはありませんか。最近は様々な新しいサービスが生まれています。特に最近ならAIを使ったビジネスでしょうか。しかし、詳しく理解していないのだが、経営者からの説明に何となく分かったようになっていることもあるでしょう。それに銀行員として勉強不足だと思われたくない心理も働くと思います。
立場上非常によく理解できるのですが、何と思われようとも納得いくまで説明を求めたほうがいいです。
経営者の立場になってみる
経営者の立場になって考えてみるのもいいでしょう。起業したばかりであったり、最近売上高が減少いていたりすれば、売上高を架空計上してでも成長力のある企業に見せようとするかもしれません。
最近、融資の相談を受けた際、実行までに時間を要したり、書類の提出を求めたりした場合、これからの融資が厳しいと感じ、スムーズにいくよう粉飾するかもしれないと考えていいでしょう。
また。経営者が地元で影響力のある方だからといって信用できるともいえません。むしろそんな立場を守りたくて粉飾をしていることも十分にあり得ます。
意見を言いやすい雰囲気づくり
銀行であれば担当者から支店長、そして本部の審査部(融資部)の行員も決算書を見るわけです。誰か一人は決算書の違和感を持ったかもしれません。特に支店で融資先と接する行員は決算書だけでなく、経営者の説明、製造現場などを見ていますから。
しかし、粉飾決算が疑われても言いづらい雰囲気はないでしょうか。もし数期前から粉飾決算が疑われることになれば、これまで気が付かなかったのかと責められるのを避けたいと考えるでしょう。これまでの融資実行が粉飾された決算書をもとにしていることを認められないかもしれません。
しかし、見て見ぬふりを振れば問題は大きくなり、自行だけでなく融資先企業にもデメリットがあります。
まとめ
資金調達方法はいろいろありますが、中小企業にとっては銀行からの融資が中心になります。だからこそ、経営者は粉飾決算を行ってでも融資を受けたい、銀行との良好な関係を維持したいと考えます。銀行員はそういう視点を持ちながら決算書を分析しましょう。
そして、決算書に違和感があったら、1人で判断せず必ず複数でチェックするようにしましょう。その結果として銀行の被害は最小限に抑えられますし、融資先企業の再建にも貢献できる可能性が高くなります。
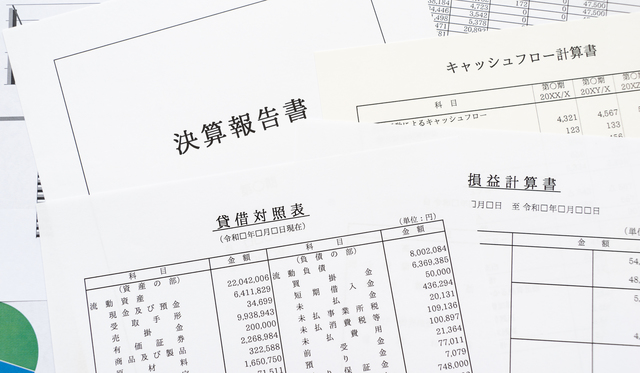


コメント