粉飾決算とは
粉飾決算とは、不正な会計処理によって故意に企業の損益状況や財政状態を実際よりも良く見せる行為をいいます。例えば、損益計算書が赤字なら黒字にすることです。
逆粉飾決算とは
逆粉飾決算という言葉もあります。それは逆に実際よりも利益を過少にする行為です。
このブログでは銀行員向けに書いておりますので、赤字を黒字にするなど通常の粉飾決算を中心にご説明していきます。
なぜ粉飾決算をするのか
粉飾決算・逆粉飾決算、どちらも不正な経理処理によって決算内容を歪める行為です。それを承知の上で行う理由は次のとおりです。
粉飾決算
融資先が粉飾決算を行う最大の理由は、銀行からの信用を失いたくないからでしょう。赤字決算が続けば返済能力に懸念があると見なされ融資には消極的になります。
本来、赤字決算に陥った中小企業の経営者は、早期に経営改善を進める必要がありますし、銀行に簡単なものであっても経営改善計画書を提出した方がいいでしょう。
しかし、短期間で黒字転換できるとは限りませんし、銀行の対応が豹変するのではと不安で言い出しにくいのです。
「どうせ決算書がすべての銀行、ここで本当の数字を出したら融資をしてくれないのだから粉飾すればいい。これから頑張って経営を立て直し、後で元に戻せばいいのだから」と考えます。信用を維持する手っ取り早い対応策は粉飾決算と思いこむのです。
ひどい経営者になると、経営改善なんて面倒でやりたくない、このまま銀行から融資を受けて継続していきたいと考える者までいます。
中小企業においては、そのような行為に反対する意見が部下から出ることは少ないでしょう。
逆粉飾決算
逆粉飾決算は利益を減らす行為ですから、利益が出すぎて少しでも税金を減らしたい場合に行われます。当然これは脱税です。
利益の30%以上を法人税等で取られてしまうのですから、経営者からすれば面白くはないと思います。そこで逆粉飾決算に手を出してしまいます。
粉飾決算の手法
粉飾決算・逆粉飾決算の代表的な方法をいくつかご紹介します。
粉飾決算の代表的な手法
粉飾決算の代表的な手法はこの2つです。
架空売上高計上
実際には存在しない売上高を計上する方法です。多額の粉飾がしやすいですし、特に売上減少が続いている中小企業であれば増加しているように装うこともできます。ただ、消費税が負担となってきます。
在庫の水増し
在庫を増やせばそれだけ売上原価が減少するため粉飾方法としてよく使われます。しかも売上高とは違い消費税に影響が出ません。
仕入未計上
本来、今期の仕入として発生しているものを翌期計上にするのですから利益を増やすことができます。
逆粉飾決算の代表的な手法
逆粉飾決算の方法は次のとおりです。なお、これは脱税行為になりますから、絶対に行わないでください。
売上高の翌期計上
本来今期の売上高を翌期に計上します。
架空仕入計上
売上原価の大半を占める仕入(業種によっては外注費)を架空で計上します。あるいは翌期に発生した分を前倒し計上します。
在庫過少計上
粉飾決算で在庫を増やすと利益が増えると申しましたが、逆に減らすことで利益を減らすことができます。
粉飾決算はなくならないし手口は進歩している
銀行に対して嘘の数字で作成した決算書を提出し、融資を受けた場合、企業の代表者などは詐欺罪などの罪に問われる可能性があります。
「粉飾決算なんてどこでもやってるでしょ?」などと甘い考えを持った経営者はいますが、粉飾決算で銀行を騙した企業の代表取締役が逮捕されるケースが増えてきました。2017年3月に自己破産を申請して倒産した企業の代表取締役は懲役6年の実刑判決を受けました。
しかし、そんなリスクがあっても経営者は自社の資金繰り改善を目的に手を出してきます。報道されないだけで粉飾決算は多くの企業で行われています。
銀行も大きな被害を受けます。仮に1億円回収不能になったとしましょう。単純な説明ですが、それを回収するためには新たに預金を100億円集めて1年間1%で融資しなければなりません。現実には預金利息や銀行の経費が発生しますからより多くの預金と融資が必要ですが。
電卓をたたいて経営分析を行っていた昔とは大きく異なり、現在では企業から受け取った決算書の経営分析結果が自動的に還元されます。しかし、それでも粉飾決算による被害が発生します。粉飾決算の手口も(悪い意味で)進歩しているのです。したがって、銀行員が自分で決算書を分析する能力を身につける必要がありますし、決算書の違和感に気付く必要があります。
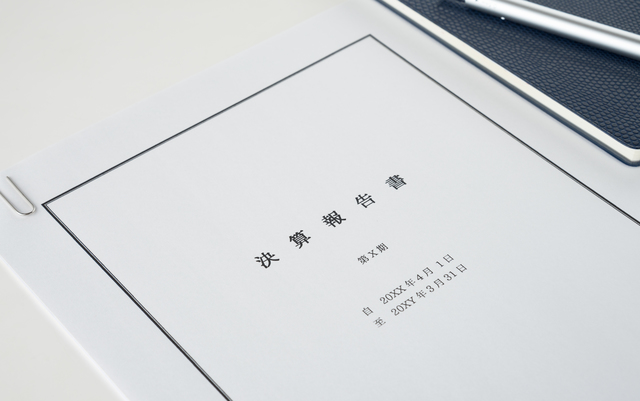


コメント